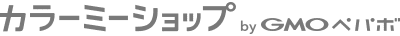ジェイエムウエストンは靴のバッハである
常々、筆者がジェイエムウエストンに対して抱いていた印象。それは「バッハみたいだな」ということです。モーツァルトやベートーベンには失敗作を存在します。しかし、多作家で若い頃から65歳で没する前年まで旺盛に創作を続けていたにもかかわらず、小品から大作まで例外なく傑出したバッハの諸作品は、ネガティブに評価されることがありません。つまりは批判を寄せ付けないほど、すべてが高い次元で完成されているということ。画家ならレンブランドとかベラスケスが、やはりそんな存在であるように思います。ジェイエムウエストン(以下、ウエストン)についても、筆者はネガティブにいわれるのを聞いたことがないのです。コンフォタブルな木型と細部まで計算されたデザインとの絶妙なバランス、一流タンナーによるトップグレードの革の、それも最も留良質な部位のみを使用するという厳格な姿勢、すこぶる高度な製靴技術と徹底したクオリティコントロール、4mmピッチ設定(通常は5mmピッチ)のサイズと数段階のウィズ(ローファーでは6段階も!)という顧客重視のブランド哲学と不動のブランドステータス…と、全ての点でウエストンは完璧だと筆者は考えます。まぁ、あまりの優等生ゆえに敬遠する人もいらっしゃるでしょうが、それはもったいない。優等生とはいえ味気なさとは無縁で、むしろバッハの音楽と同様、知るほどにその味に魅せられていく。そんな魅力がウエストンには備わっているからです。
1891年、エドゥアール・ブランシャール氏がパリ近郊のリモージュ(現在もこの地に工場があります)にブランシャール社を築いたのがウエストンの事始めです。当初は機械式による量産靴を手掛けていましたが、アメリカでグットイヤー製法を研究していた息子ユージェーヌ氏の帰国後、機械式と職人の手仕事を積極的に組み合わせた独自の生産システムを構築。1922年にパリのクーセル通りに直営第1号を開き、初めて「J.M.WESTON」の名を世に送り出し、その10年後には現在の本店であるシャンゼリゼ店もオープンしました。
1980年代、革底用皮革を供給していたリモージュ近郊のタンナーが経営難に陥ったことから、それを買収。ちなみに世界中のシューメーカーのうち、タンナーを抱えているのは、ウエストン以外では米レッド・ウィング(こちらは底材用ではなく、アッパー用の革を生産しています)くらいですから、これは非常に珍しいことなのです。また、その自社製の本底革はドイツ産などの原皮を1ヶ月半〜2ヶ月間、タンニン槽に浸け込んだのち、樫のチップ材と一緒に堅穴に入れ、何度か裏返しの作業を施しつつ8ヶ月〜10ヶ月寝かすという、これまた大変に珍しい技術で製革されます。誠に手のかかる、このなめし法によってできあがる革は目が詰まったものとなり、しなやかでありながら摩耗しにくいという特性を獲得します。
ウエストンについては、まだまだ書きたいことがあるのですけれど、残念ながら字数が残りわずかになってしまいました。 数々の名靴をコレクションにもつウエストンですが、やはりどれか1足をとなれば。やはり180に尽きると判断し、ここに取り上げました。昨今の靴人気をさかのぼると90年代初め頃に至りますが、ファッション業界などほんの一部の人たちは別として、当時、一般の人々が「高級靴とはかくなりや」と開眼できたのは、このローファーがあったからだと思うのです。そうした歴史的な貢献を含めて、やはりウエストンはバッハのように偉大な存在なのだと思うのです。
出典:靴を読むより
【令和3年5月2日】更新
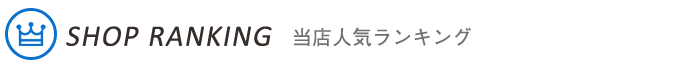
カテゴリーから探す
コンテンツを見る
- Concept
- One point
- About us
- よくある質問(FAQ)
- 失敗しないサイズ選び5選
- 下取りキャンペーン調査結果
- 革靴を激安で買う方法5選
- ヒール交換は本当にお得なのか?
- 革靴を磨かない人向けの手入れ法
- 冠婚葬祭用の靴はいらない
- 豆知識【なぜ値段が違うの?】
- お客様からの声_2021年1月13日更新
- 革靴が濡れた際の対処法【梅雨編】
- 歩きやすい靴とは?
- 姉妹店開店記念セール
- カード決済が不安なお客様へ
- 革靴のお得な捨て方
- 革靴にカビが生えたら読む記事
- 革靴のお手入れ方法
- 必読 ビジネスシューズのコスパ
- 革靴を買う心得<百貨店催事編>
- ビジネスシューズの通気性について
- ビジネスシューズのおすすめ
- ビジネスシューズが安い店
- ビジネスシューズ おすすめブランド5選
- ビジネスシューズに使えるスニーカー5選
- ビジネスシューズの紐の通し方と結び方
- ビジネスシューズで使うウォーキングシューズ5選
- ビジネスシューズ 防水性能について
- 歩きやすいビジネスシューズ選び
- ビジネスシューズの形や種類について
- ビジネスシューズの底剥がれについて
- ビジネスシューズ向けインソール
- ビジネスシューズのエアーソールについて
- ビジネスシューズのサイズ表記(ワイズ編)
- オールソール交換について
- 革靴の種類について
- 革靴の用語辞典 基礎編
- お客様のお声を実行します
- 同梱されている「おまけ」について
- 新規店舗出店のお知らせ
- ビジネスシューズ選び 痛い場合
- ビジネスシューズがきつい場合の対応策
- 靴メーカーがどんどん減っています
- 歩きやすいビジネスシューズ
- 踵がすり減ると身体が不調になる恐れがあります
- 紳士靴のセールについて
- お客様のお宅へご訪問してきました
- 訳アリ品販売を始めます
- CROCKETT&JONESはOEMメーカーだった
- John Lobb(ジョン・ロブ)の逸話
- Clarksクラークス(イギリス)編〜世界のブランド紹介〜
- Aldenオールデン(アメリカ)〜世界のブランド紹介〜
- Berlutiベルルッティ(フランス)〜世界のブランド紹介〜
- フィッテングのポイント
- 靴の手入れと保存について
- ボロネーゼ製法の靴は足に吸い付く
- 靴辞典 製法についてステッチダウン式製法
- ネット通販でも安心に革靴が買える店
- 靴辞典 製法についてグッドイヤーウェルト
- 靴辞典 製法についてマッケィ式製法
- 靴辞典 製法についてノルウィージャンウェルト式製法
- 靴辞典 製法についてセメント式製法
- 靴辞典 エスパドリーユの由来
- 紳士靴を買うときに読む記事
- 世界のブランド_Henry Maxwell(ヘンリーマクスウェル)紹介
- Eduard Meierエドワード・マイヤー(ドイツ)編〜世界のブランド紹介〜
- Enzo Bonafeエンツォ・ボナフェ(イタリア)編〜世界のブランド紹介〜
- Silvano Lattanziシルバノ・ラッタンジ(イタリア)編〜世界のブランド紹介〜
- PARABOOT(パラブーツ)〜世界のブランド紹介〜
- Stefano Bemer(ステファノ ベーメル)〜世界のブランド〜
- George Cleverleyジョージクレバリー(イギリス)編〜世界のブランド紹介〜
- Patrick Cox(パトリック コックス)イギリス〜世界のブランド〜
- Birkenstock(ビルケンシュトック)ドイツ〜世界のブランド〜
- Duckling(ダックリン)イタリア〜世界のブランド〜
- Trippen(トリッペン)ドイツ〜世界のブランド〜
- Pouksen Skone(ポールセンスコーン)〜イギリス〜世界のブランド〜
- 本革製紳士靴が5,500円で買えます
- オールデンとホーウィンの小話
- メルカリ、ラクマよりも安い革靴(新品)があります
- お客様のお宅へご訪問してきました2
- 姉妹店開店 記念品を同梱します
- 世の中に紳士ビジネス靴分野で貢献します
- お試し価格の商品を多数掲載中
- 大変長らくお待たせしました
- 4950円(税込み)で本革ビジネスシューズお買い求めいただけます
- グッドイヤーウェルト製法商品
- 靴底の豆知識
- 靴底の豆知識2
- 梱包用ダンボール使用中止のお知らせ
- 靴底の豆知識3
- 小網神社に毎月必ず参拝してます
- 靴店はひと昔前の酒屋さんの様になります
- 購入フォーム「お客様情報」入力がスムーズになります
- 靴のエコー紹介動画をyoutubeに投稿
- 靴の中敷きが波を打っているんです。SOSのお電話
- 28cm、29cmまでのキングサイズも同一価格です
- 業務効率化の為本社移転します
- SHOES from ITALY 67th
- よもぎ蒸しを初体験しました
- 2月でネット販売1周年を迎えました
- コロナ禍で靴製造業界は大変なことになっています
- フローシャイムの「コブラヴァンプ」は何故”コブラ”なのか?
- エッセイ「男の靴 オンナの目」
- 革の基礎知識
- 徹底解説”プロの靴磨き”
- 起毛素材の靴のお手入れ
- 皮が革になるまで
- 靴磨きの道具について
- 靴のエバーグリーン、それはブルックスのローファーである
- デッキモカシンは実は機能の固まりである
- 冷えない&蒸れない!ゴアテックスブーティの実力
- トリッカーズのモンキーブーツをジット見てください。サル顔に見えますか?
- パンクをキメたくば、これを履け!
- 「道具」にしてこそ、格好いい
- Stefano Bemer
- ジェイエムウエストンは靴のバッハである